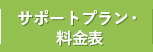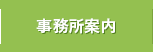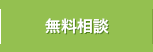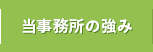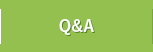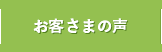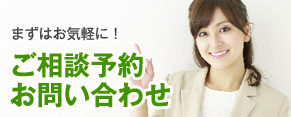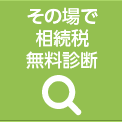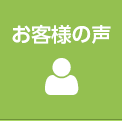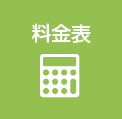「おひとりさま」時代の老後と相続 ~“孤立”は他人事ではない? 今からできる安心への備え~
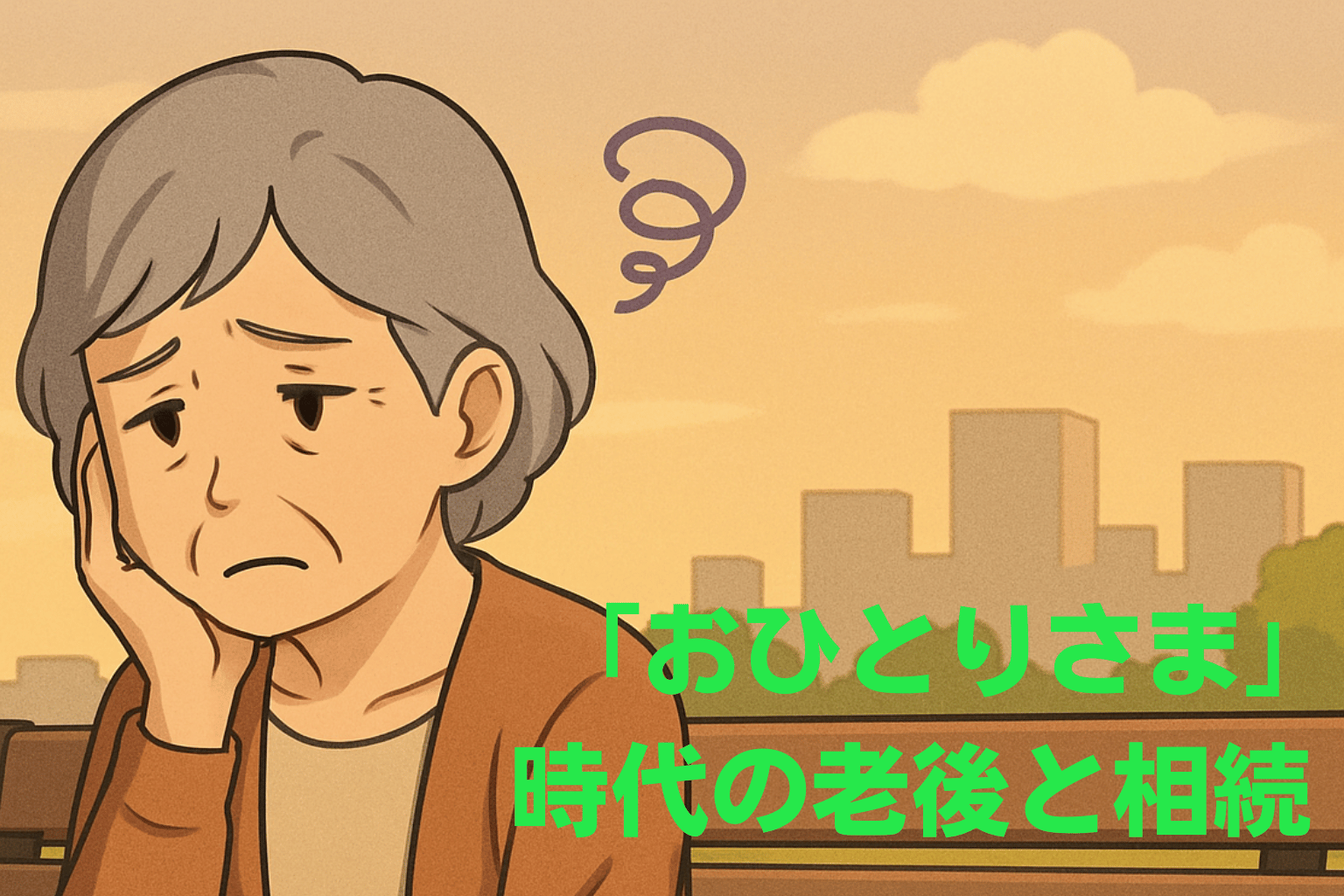
目次
- はじめに:「ひとり」の時代の不安と相続
- あなたの周りでも? 静かに広がる「孤立」のかたち
- なぜ今、「孤立」が問題になっているの? ~個人の問題だけではない背景~
- 「孤立」が招くかもしれない、将来の心配ごと
- 相続にも影響が? 「おひとりさま」時代の備え
- 相続対策だけじゃない。「つながり」が未来を支える…でも無理は禁物
- 今からできること:完璧じゃなくていい、小さな一歩から
- 孤独・孤立と相続に関するよくあるご質問(FAQ)
- まとめ:未来への備えは、財産と「つながり」の両輪で
- 相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
はじめに:「ひとり」の時代の不安と相続
「最近、ご近所付き合いもめっきり減ったなあ」「子どもたちは遠くに住んでいるし、将来もしパートナーに先立たれたら、自分は一人でどうなるんだろう…」。そんな風に、ふとした時に将来のことを考えて、少し心細くなることはありませんか? 今、私たちの社会では、年齢に関わらず「ひとり」で暮らす方や、「寂しいな」と感じる方が増えていると言われています。実は、この「ひとり」や「つながりの希薄さ」といった問題は、ご自身の老後の暮らしや、大切な財産を引き継ぐ「相続」にも、思った以上に深く関わってくる可能性があるのです。この記事では、なぜ今「孤立」が問題になっているのか、それが私たちの将来や相続にどう影響するのか、そして安心して老後を迎えるために、お金の準備だけでなく「人とのつながり」がいかに大切か、今日からできる備えについて、分かりやすくお伝えしていきます。ただし、この問題は非常に複雑で、この記事だけで完璧な答えが見つかるわけではないことも、心に留めておいていただければ幸いです。
あなたの周りでも? 静かに広がる「孤立」のかたち
まず、「孤独」と「孤立」という言葉について、少し整理しておきましょう。「孤独」というのは、「寂しいな」「ひとりぼっちだな」と感じる、どちらかというと心の中の気持ちのことです。一方、「孤立」は、実際に周りに頼れる人が少なかったり、社会との接点がほとんどなかったりする、客観的な状態を指します。もちろん、一人でいる時間を大切にする方、静かに過ごすことを好む方もいらっしゃいます。問題なのは、本人が望まないのに孤立してしまい、困ったときに誰にも頼れず、助けを求められない状況です。
参考資料によると、「しばしば孤独を感じる」と答えた人は、20代から50代で10%を超えており、若い世代でも決して少なくありません。また、「相談相手がいない」という人も、同じく20代から50代で10%を超え、特に高齢になるとその割合が増える傾向にあります。昔は大家族が当たり前で、地域での助け合いも今よりは身近でした。しかし今は、核家族化が進み、「ひとり暮らし」の世帯が非常に増えています。特に65歳以上の方では、男性の約15%、女性の約22%がひとり暮らしというデータもあります。これは、もはや特別なケースではなく、私たちのすぐ隣にある現実と言えるでしょう。
なぜ今、「孤立」が問題になっているの? ~個人の問題だけではない背景~
昔と比べて、私たちの暮らしはずいぶん便利になりました。インターネットがあれば買い物もできるし、遠くの人とも連絡が取れます。でも、その反面、わざわざ外に出かけたり、誰かと直接会ったりする機会が減ってしまった、と感じる方もいるかもしれません。以前は、町内会の集まりや子どもの学校行事など、意識しなくても人と顔を合わせる場面がたくさんありました。しかし今は、そうした「場」が減り、自分から積極的に動かないと、なかなか人とつながるきっかけが得られない時代になっているのかもしれません。
さらに、結婚しない人が増えたり、退職して会社とのつながりがなくなったりと、ライフスタイルも多様化しています。また、地域のつながりが薄れたり、経済的な理由で社会参加が難しくなったりすることも影響しています。このように、「孤立」は単に個人の性格や選択だけの問題ではなく、社会全体の構造変化、経済状況、地域コミュニティの変化といった、複合的な要因が絡み合って生まれているのです。誰か特定の人が悪いわけではなく、社会全体が変化してきた結果、孤立しやすい状況が生まれている、と理解することが大切です。
「孤立」が招くかもしれない、将来の心配ごと
では、もし望まない「孤立」状態になってしまった場合、具体的にどんな心配ごとが出てくるのでしょうか。まず、孤立していると、心や体の調子を崩しやすくなると言われています。寂しさやストレスが続くと、気持ちが落ち込んだり、生活習慣が乱れたりする原因にもなりかねません。ある研究では、社会的な孤立は、1日にタバコを15本吸うのと同じくらい健康に悪い、とも指摘されています。これは決して大げさな話ではありません。
そして、もっと現実的な問題として、いざという時に頼れる人がいない、という状況が考えられます。例えば、急に病気になったり、ケガをしてしまったりした時、誰に連絡すればいいのか。入院や手続きが必要になった時、誰が手伝ってくれるのか。また、年齢を重ねて判断能力が少し衰えてきた場合に、大切なお金の管理や契約ごとを誰にお願いすればいいのか、といった切実な問題も出てくるかもしれません。
相続にも影響が? 「おひとりさま」時代の備え
こうした孤立の問題は、ご自身の財産を次の世代に引き継ぐ「相続」の場面でも、無視できない影響を与えます。例えば、身寄りのない方が亡くなられた場合、誰がその方の財産を整理し、手続きを進めるのか、という問題が出てきます。法律で定められた相続人がいればその方が手続きを行いますが、相続人が誰もいなかったり、いたとしても長年連絡を取っておらず疎遠だったりすると、手続きが非常に複雑になったり、多くの時間がかかったりすることがあります。実際に、相続人がいないために国のものとなる財産は年々増えています。
また、ご自身が築き上げてきた大切な財産を、誰に、どのように遺したいのか。その意思を明確にしておかないと、ご自身の望まない形で財産が処理されてしまう可能性もゼロではありません。特に、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、どちらか一方が亡くなった後の相続(二次相続)のことまで考えて準備しておくことが大切です。これからの時代は、「家族がいて当たり前」「誰かが自然とやってくれるだろう」という考え方だけでは、少し心もとない場面が増えてくるかもしれないのです。
相続対策だけじゃない。「つながり」が未来を支える…でも無理は禁物
ここまで読んで、「じゃあ、どうすればいいの?」と不安に思われたかもしれません。もちろん、相続税の対策や、遺言書の作成といった法的な準備は非常に重要です。私たち税理士も、そのお手伝いをさせていただいています。しかし、これからの時代、財産の準備と同じくらい、『人とのつながり』を意識しておくことが、ご自身の老後の安心を支える、もう一つの大切な要素になってくると考えられます。
ただし、ここで注意したいのは、「つながり」が必ずしも良いものとは限らないということです。無理をして価値観の合わない人と付き合ったり、気を使うばかりの関係だったりすると、かえってストレスが溜まり、孤独感を深めてしまうことだってあります。大切なのは、数ではなく「質」であり、ご自身にとって心地よい距離感を見つけること。そして、「つながりを持たなければならない」とプレッシャーに感じる必要はありません。人との関わり方は人それぞれです。
それでも、いざという時に頼れる人がいるという安心感や、日々のちょっとした会話がもたらす心の張りは、やはり大切です。それは、家族や親戚だけでなく、信頼できる友人、地域の人々、そして私たちのような専門家との関係も含まれます。お金やモノの準備と、自分に合った「人とのつながり」の準備。この二つを、焦らず、ご自身のペースで考えていくことが、これからの時代には求められるのではないでしょうか。
今からできること:完璧じゃなくていい、小さな一歩から
「つながりが大事なのは分かったけど、具体的に何をすれば…?」「人付き合いは元々苦手で…」と感じる方もいらっしゃるでしょう。大丈夫です。大切なのは、完璧を目指すのではなく、できることから少しずつ始めることです。そして、覚えておいていただきたいのは、孤立は個人の問題だけでなく、社会の変化も背景にあるということ。ですから、一人で全てを抱え込む必要はありませんし、すぐに解決する特効薬があるわけでもありません。
では、具体的にどんなことから始められるでしょうか?
- まずは、知ることから:
お住まいの地域には、どんな集まりや活動があるのか、市の広報誌や公民館の掲示板などを少し気にして見てみましょう。高齢者向けのサロンや、趣味のサークルなど、意外な発見があるかもしれません。また、困ったときに相談できる公的な窓口(各区のいきいき支援センター(地域包括支援センター)など)の連絡先を控えておくだけでも、心の備えになります。名古屋市には、身寄りのない高齢者の方などの葬儀や納骨、家財処分などを支援する「あんしんエンディングサポート事業」という制度もあります。利用には条件がありますが、こうした公的なサポートがあることを知っておくだけでも、少し安心できるかもしれませんね。(事業の詳細は、こちらの記事や名古屋市のウェブサイトでご確認いただけます。)
- 無理のない範囲で、外と接点をもつ:
毎日でなくても構いません。週に一度でも、散歩のついでに近所のお店に寄ってみる、顔見知りの人に挨拶してみる、といった小さなことから始めてみましょう。「誰かとつながろう!」と意気込みすぎず、「ちょっと顔を出す」「少し話してみる」くらいの気軽な気持ちでいることが、長続きのコツかもしれません。図書館など、人がいるけれど直接話さなくても良い場所に出かけるのも気分転換になります。
- 「おまかせ」ではなく、「相談」を:
ご自身の健康のこと、お金のこと、そして相続のこと。心配なことがあれば、「いつか誰かが気づいてくれるだろう」と待つのではなく、早めに信頼できる人に相談する習慣をつけましょう。ご家族やご友人でも良いですし、内容によっては、私たちのような税理士や、弁護士、司法書士といった専門家を頼ることも考えてみてください。早めに相談することで、より多くの選択肢の中から、ご自身に合った方法を見つけやすくなります。問題を整理するだけでも、気持ちが楽になることがあります。
孤独・孤立と相続に関するよくあるご質問(FAQ)
- Q1: 「孤立」しているかどうか、自分でチェックする方法はありますか?
A1: 明確な基準はありませんが、以下のような点を振り返ってみるとよいかもしれません。
- この1週間で、家族以外の人と、あなたにとって意味のある会話(挨拶だけでなく)をしましたか?
- 困ったことがあった時に、気兼ねなく相談できる人はいますか?(家族以外で)
- 地域活動や趣味の集まりなど、定期的に参加しているものはありますか?(義務感ではなく、ある程度楽しめていますか?)
- もし2日間、誰とも話さなかったとしても、特に寂しさや不安を感じませんか?
もし、「いいえ」が多かったり、「気になる」と感じたりする場合は、少しずつでも人との心地よい接点を持つことを意識してみると良いかもしれません。無理は禁物です。
- Q2: 相続の準備として、具体的に何をすれば良いですか?
A2: まずは、ご自身の財産(預貯金、不動産、有価証券など)を正確に把握することから始めましょう。次に、誰にどのように財産を遺したいか、ご自身の意思を明確にすることが大切です。そのための有効な手段が「遺言書」の作成です。遺言書には種類があり、作成方法にもルールがありますので注意が必要です。また、相続税がかかる可能性がある場合は、事前に税額を試算し、納税資金の準備や適切な対策を検討することも重要になります。加えて、この記事でお伝えしたように、信頼できる相談相手(家族、友人、専門家など)を見つけておくことも、広い意味での相続準備と言えるでしょう。具体的な進め方については、税理士などの専門家にご相談いただくのが確実です。当事務所では初回60分の無料相談で、こうした準備の進め方についてもアドバイスさせていただいております。
- Q3: 人付き合いが苦手なのですが、それでも何かできますか?
A3: もちろんです。無理に社交的になる必要はありません。人付き合いが苦手な方でもできることはあります。例えば、直接的な交流でなくても、興味のある分野のオンラインコミュニティに参加してみる、図書館で静かに過ごす時間を楽しむ、といった方法もあります。地域のボランティア活動に、自分の得意なことを活かせる形で短時間だけ参加してみるのも良いかもしれません。大切なのは、ご自身にとって負担が少なく、続けやすい方法で、社会との「細くても確かなつながり」を感じられることです。焦らず、ご自身のペースで、心地よいと感じる関わり方を探してみてください。
まとめ:未来への備えは、財産と「つながり」の両輪で
私たちの社会は、気づかないうちに大きく変化しています。「ひとり」でいることが珍しくなくなり、便利になった一方で、人と人とのつながりが自然には生まれにくい時代になりました。「孤独」や「孤立」は、決して他人事ではなく、私たちの老後の暮らしや、大切な相続にも関わってくる身近な問題です。そして、その背景には、個人の選択だけでなく、社会全体の構造変化があることも忘れてはいけません。
将来の安心のためには、財産の準備はもちろんのこと、いざという時に頼れる人との、自分に合った「つながり」を意識しておくことが、ますます重要になってきます。完璧な人間関係を築こうと焦る必要はありませんし、この記事が提供できるのは、あくまで考える「きっかけ」です。まずは現状を知り、ご自身にできる小さな一歩から、無理なく始めてみませんか?
相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
この記事を読んで、ご自身の老後や相続について、少しでも考えるきっかけになったのであれば幸いです。相続は、時に複雑で、精神的な負担も大きいものです。特に、身近に相談できる方が少ない場合、その不安は一層大きくなることでしょう。
名古屋相続税無料診断センターでは、相続税申告の専門家として、皆様のお悩みに寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。相続財産の評価、遺産分割のご相談、相続税申告書の作成・提出はもちろん、生前の相続対策や遺言書作成のサポートまで、幅広く対応しております。初回のご相談(60分)は無料ですので、「何から始めればいいかわからない」「相続税がいくらかかるか心配」といった漠然としたご不安でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方は 0120-339-719 までご連絡ください。
参考資料
- 石田光規(早稲田大学)「拡大する孤独・孤立問題の現状と課題」財務総合政策研究所 ランチミーティング資料(2025年4月3日) https://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/fy2025/lm20250403.pdf
- 内閣府「令和4年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)」 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/04pdf_index.html
- 名古屋市社会福祉協議会「名古屋市あんしんエンディングサポート事業」 (内部リンク先の記事: https://www.souzoku-stf.com/anshin-ending/)
- 名古屋市「名古屋市あんしんエンディングサポート事業(暮らしの情報)」 https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000157172.html
著者情報
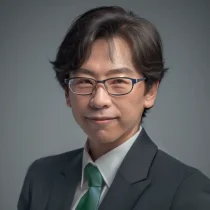
- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
-
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
最新の投稿
お知らせの最新記事
- 【業務提携のお知らせ】READYFOR株式会社と遺贈寄付領域で提携
- 2024年12月27日(金)から2025年1月5日(日)まで休業いたします。
- 相続税のカギ!?基準年利率をわかりやすく解説!
- 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶ?違いを徹底比較
- 相続・不動産の悩みを解決!2024年秋の無料相談会のお知らせ
- あなたの相続、大丈夫? 実は知らないと損をする「相続リテラシー」の落とし穴
- 愛知県民必見!路線価上昇で相続税リスクが高まっている?
- 国庫帰属、本当に最後の手段?あなたの土地に眠る「意外な価値」を見つける方法
- 36.7%が経験する相続の後悔…終活における家族間のコミュニケーションの大切さ
- 一人暮らしの高齢者も安心!名古屋市「あんしんエンディングサポート事業」のご紹介
- 相続についての難解な用語をサクッと解説
- 相続の「かかりつけの税理士」を目指して
- 日本の相続税の特徴と国際比較
- 所有者不明土地問題の解決に向けた改正登記制度の概要と影響
- 相続手続きの複雑さ・大変さを克明に描いたNHKの相続手続き体験談のご紹介
- 実は9割の相続税申告、土地評価に強い税理士に依頼した方が良い理由
- 相続税・家族信託 無料セミナー・相談会 11/13(水) 大垣共立銀行本山支店
- 8月24日・25日相続セミナー・相談会を開催いたしました
- 遺産相続・遺言・終活無料相談会 5/19(日) 名古屋市千種区見付コミュニティセンター
- 遺産相続・遺言・終活無料相談会 3/17(日) 名古屋市名東生涯学習センター
- 遺産相続・遺言・終活無料相談会 1/20(日) 名古屋市守山生涯学習センター
- 相続税・遺言無料相談会 11/4(日) 名古屋市中川生涯学習センター
- 【Q&A】土地の相続をしたいです。何から始めればいいでしょうか?
- ホームページをリニューアルオープンいたしました!
コラムの最新記事
- 【2025年4月開始】相続手続きが楽になる!?「口座管理法」と「相続時口座照会」とは?
- 【名古屋市】令和7年4月から「名寄帳(なよせちょう)」交付開始!相続手続きが劇的に変わる!
- 相続税調査はどう変わる?国税庁のAI活用、その現状と将来展望
- 相続人がいない場合、財産はどこへ? 特別縁故者や国庫帰属までのまるわかり案内
- デジタル遺産の整理で始める安心の相続:デジタル終活完全ガイド
- 【令和5年度版】相続税は厳しくなる?愛知県の税務調査と申告の最新動向を徹底解説
- 2024年12月27日(金)から2025年1月5日(日)まで休業いたします。
- 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶ?違いを徹底比較
- 相続した土地、国に返還したい…でもちょっと待って!その前に確認!
- あなたの相続、大丈夫? 実は知らないと損をする「相続リテラシー」の落とし穴
- 愛知県民必見!路線価上昇で相続税リスクが高まっている?
- 国庫帰属、本当に最後の手段?あなたの土地に眠る「意外な価値」を見つける方法
- 36.7%が経験する相続の後悔…終活における家族間のコミュニケーションの大切さ
- 一人暮らしの高齢者も安心!名古屋市「あんしんエンディングサポート事業」のご紹介
- 相続についての難解な用語をサクッと解説
- 相続の「かかりつけの税理士」を目指して
- 日本の相続税の特徴と国際比較
- 所有者不明土地問題の解決に向けた改正登記制度の概要と影響
- 相続手続きの複雑さ・大変さを克明に描いたNHKの相続手続き体験談のご紹介
- 実は9割の相続税申告、土地評価に強い税理士に依頼した方が良い理由
- 【負動産】とは何か?その問題と解決策 | 名古屋相続税無料診断センター
- 【相続税の計算】自分で簡単にできる方法を税理士が分かりやすく解説
- 【相続税】専門税理士がむずかしい言葉を分かりやすく説明する件
- 【相続対策】節税だけでない、事前に必要な4つの対策
- 【最重要】相続税がゼロでも相続税申告が必要な件
- 【これで納得】相続税のお尋ねがきたときの対応方法
- 【事実】相続人に未成年者がいる場合の遺産分割の手続き
- 【最重要】相続が起こる前に抑えておきたい相続税の基礎控除
- 【名古屋市千種区:相続相談/配偶者居住権で将来の相続に備える】
- 名古屋市 相続税専門税理士 申告の現場より。タンス預金に注意!!
- 法律を知って得する「家なき子特例」その5
- 法律を知って得する「家なき子特例」その4
- 法律を知って得する「家なき子特例」その3
- 法律を知って得する「家なき子特例」その2
- 法律を知って得する「家なき子特例」その1